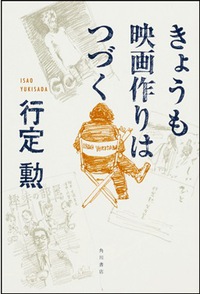2011年08月14日
ぼくは12歳

新編 ぼくは12歳 (ちくま文庫)
岡 真史
文庫: 285ページ
出版社: 筑摩書房 (1985/12)
ISBN-10: 4480020292
ISBN-13: 978-4480020291
発売日: 1985/12
きみは「さよなら」と
一言かいた
おき手紙をおいて
いってしまったね
でもぼくは
なかなかったよ
だって
世界なんてせまいもの
七月の夕刻、団地から投身した少年の遺した詩と、
両親(父親は高史明氏)と読者の間で交わされた往復書簡の一部が掲載されています。
スタッフ吉田です。
最近読み終えた中で心に残ったのがこの「ぼくは12歳」です。
同タイトルで同じく筑摩書房より1976年に刊行された本を元に再編集され新編としてまとめられたものです。
1962年生まれの岡真史くんが書き溜めていた詩や、学校で書いた読書感想文などが前半に。
後半は母親の岡百合子さん、父親の高史明さんの思いや、真史くんの詩集をきっかけに知り合うことになった、二人の女性との往復書簡を元に編成されています。
2008年にETV特集で放送され、爆笑問題の太田光さんが自宅を訪問された時の様子がテレビ放送され話題となったこともあります。当時視聴された方もいらっしゃるのではないでしょうか。
母親である岡百合子さんの文中の言葉を拝借するなら、真史くんは「優しい、手のかからない子」であり「茶目で陽気で、社交的」「そして本を読むことと、音楽が、特別な好きな少年」でした。掲載されている詩の中でも、これらの性格を裏付ける表現や、みずみずしい感受性、そして心の優しさが伝わってきます。この年にしては背伸びしているな、と感じられる表現が微笑ましかったり、鋭い視点にはっとさせられることがあったり、へんに技巧が凝らされておらず素直に書かれたものであればこそ一文一文が尊い透明感を備えているようです。
たとえば「ユキ」と題された作品では、
白い宝石を
どんどん空から
おっことす
でもぼくたち
もらってもしょうがない
すぐにとかしてしまうもの
空のように大事にしない
なのになぜ
空はぼくたちに
宝石をおっことすのかなあ
というように素朴な疑問が書かれていたり、一方では、自分が19さいや20さいであると設定された詩があったり、恋のことであったり、学校でのことであったり、読まれることを想定していない、自分だけの日記のような奔放さと、それに加えて寂しさのようなものも感じます。
後半の往復書簡で、ある人(本文ではOさんと表記されています)が真史くんの死は弱者としての死ではなく、誰よりも真実に生きたいがための死だった、人にまちがっていると言わせるような死ではなかったと語っています。さらに、「生きることと死ぬことのどちらが真実に対して真正面からとりくむことになるか、考えてみなければならない」とも。その言葉を高史明さんは真摯に受け止めたうえで、やはり自死を肯定することはできません。生と死はもともと一つであるべきものであり、二つに分けて立てることが真実に近づく道とは思えないのだと述べています。
往復される数々の言葉、解釈のやり取りはやがて、科学文明、思想、言葉・文学の分野にまで言及し、生きることと死ぬことについて語られていきます。
これらのやり取りは非常に興味深く、とても考えさせられるものでした。
生死には定義も答えもありません。言葉に関与することで脆弱を内包することとなりながらも人間はその運命から逃れることはできないでしょう。私たちはただ、真摯に考えることをやめないでいることによってしか生きていけないのだとも思えてきます。
最後に、この本の中でもいくつか取り上げられている、夏目漱石の作品の中から。
僕は死んだ神より生きた人間の方が好きだ。車夫でも、立ん坊でも、泥棒でも、僕が難有いと思ふ刹那の顔、即ち神ぢやないか。山でも川でも海でも、僕が崇高だと感ずる瞬間の自然、取りも直さず神ぢやないか。其外に何(ど)んな神がある。
「神は死んだ」との有名な言葉を残したのはニーチェです。
そのニーチェが生きた時代と踵を接する時代に生きた夏目漱石が、ニーチェとは正反対の方向に自由の道を見出そうとした、現代の、そしてこれからの日本でも通用する救いの視点ではないでしょうか。
夏目さんがお札になっていた理由が今頃になって少しずつ分かり始めている今日このごろです・・・・・・
最近読み終えた中で心に残ったのがこの「ぼくは12歳」です。
同タイトルで同じく筑摩書房より1976年に刊行された本を元に再編集され新編としてまとめられたものです。
1962年生まれの岡真史くんが書き溜めていた詩や、学校で書いた読書感想文などが前半に。
後半は母親の岡百合子さん、父親の高史明さんの思いや、真史くんの詩集をきっかけに知り合うことになった、二人の女性との往復書簡を元に編成されています。
2008年にETV特集で放送され、爆笑問題の太田光さんが自宅を訪問された時の様子がテレビ放送され話題となったこともあります。当時視聴された方もいらっしゃるのではないでしょうか。
母親である岡百合子さんの文中の言葉を拝借するなら、真史くんは「優しい、手のかからない子」であり「茶目で陽気で、社交的」「そして本を読むことと、音楽が、特別な好きな少年」でした。掲載されている詩の中でも、これらの性格を裏付ける表現や、みずみずしい感受性、そして心の優しさが伝わってきます。この年にしては背伸びしているな、と感じられる表現が微笑ましかったり、鋭い視点にはっとさせられることがあったり、へんに技巧が凝らされておらず素直に書かれたものであればこそ一文一文が尊い透明感を備えているようです。
たとえば「ユキ」と題された作品では、
白い宝石を
どんどん空から
おっことす
でもぼくたち
もらってもしょうがない
すぐにとかしてしまうもの
空のように大事にしない
なのになぜ
空はぼくたちに
宝石をおっことすのかなあ
というように素朴な疑問が書かれていたり、一方では、自分が19さいや20さいであると設定された詩があったり、恋のことであったり、学校でのことであったり、読まれることを想定していない、自分だけの日記のような奔放さと、それに加えて寂しさのようなものも感じます。
後半の往復書簡で、ある人(本文ではOさんと表記されています)が真史くんの死は弱者としての死ではなく、誰よりも真実に生きたいがための死だった、人にまちがっていると言わせるような死ではなかったと語っています。さらに、「生きることと死ぬことのどちらが真実に対して真正面からとりくむことになるか、考えてみなければならない」とも。その言葉を高史明さんは真摯に受け止めたうえで、やはり自死を肯定することはできません。生と死はもともと一つであるべきものであり、二つに分けて立てることが真実に近づく道とは思えないのだと述べています。
往復される数々の言葉、解釈のやり取りはやがて、科学文明、思想、言葉・文学の分野にまで言及し、生きることと死ぬことについて語られていきます。
これらのやり取りは非常に興味深く、とても考えさせられるものでした。
生死には定義も答えもありません。言葉に関与することで脆弱を内包することとなりながらも人間はその運命から逃れることはできないでしょう。私たちはただ、真摯に考えることをやめないでいることによってしか生きていけないのだとも思えてきます。
最後に、この本の中でもいくつか取り上げられている、夏目漱石の作品の中から。
僕は死んだ神より生きた人間の方が好きだ。車夫でも、立ん坊でも、泥棒でも、僕が難有いと思ふ刹那の顔、即ち神ぢやないか。山でも川でも海でも、僕が崇高だと感ずる瞬間の自然、取りも直さず神ぢやないか。其外に何(ど)んな神がある。
「神は死んだ」との有名な言葉を残したのはニーチェです。
そのニーチェが生きた時代と踵を接する時代に生きた夏目漱石が、ニーチェとは正反対の方向に自由の道を見出そうとした、現代の、そしてこれからの日本でも通用する救いの視点ではないでしょうか。
夏目さんがお札になっていた理由が今頃になって少しずつ分かり始めている今日このごろです・・・・・・

タグ :長崎書店